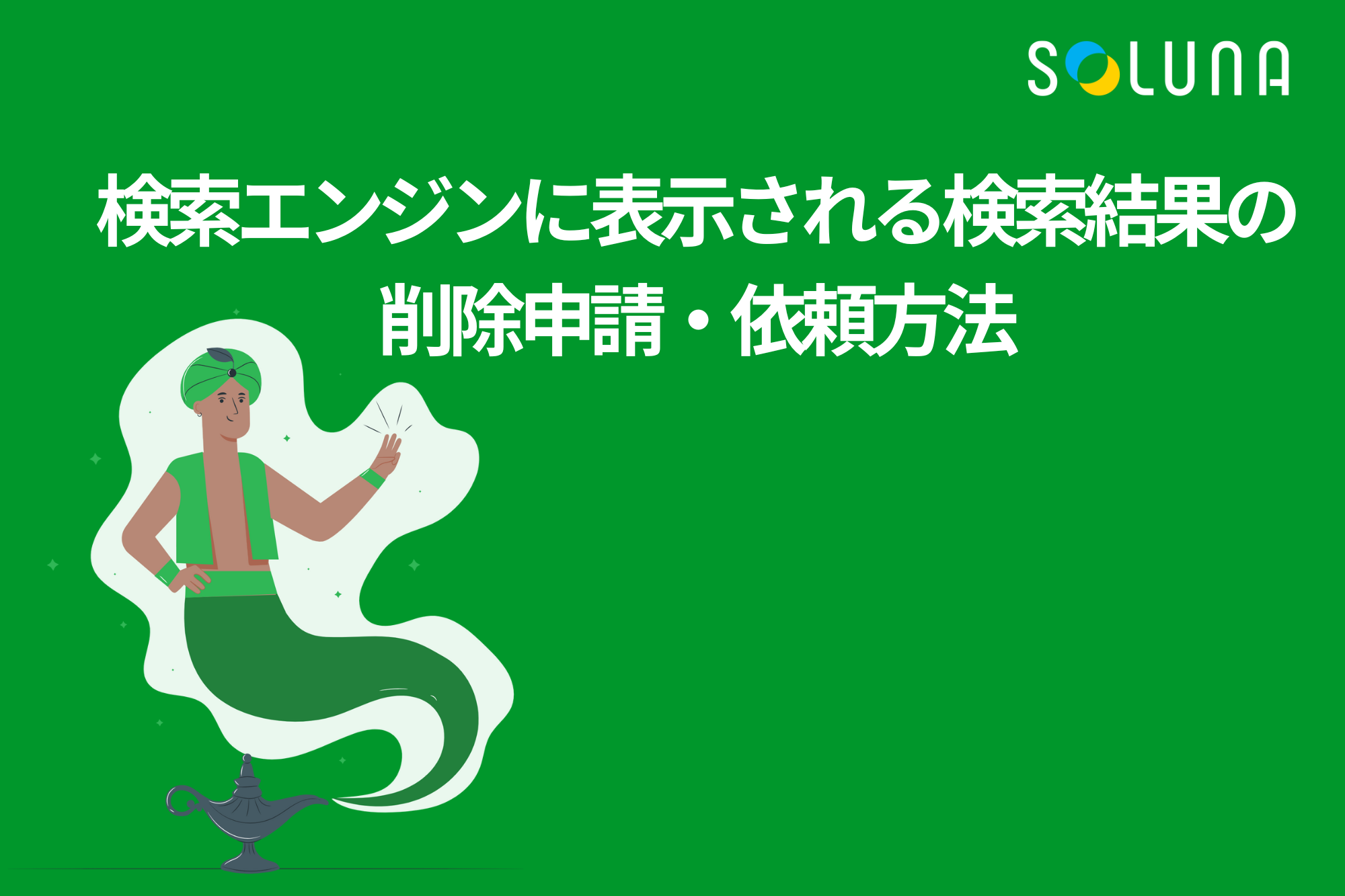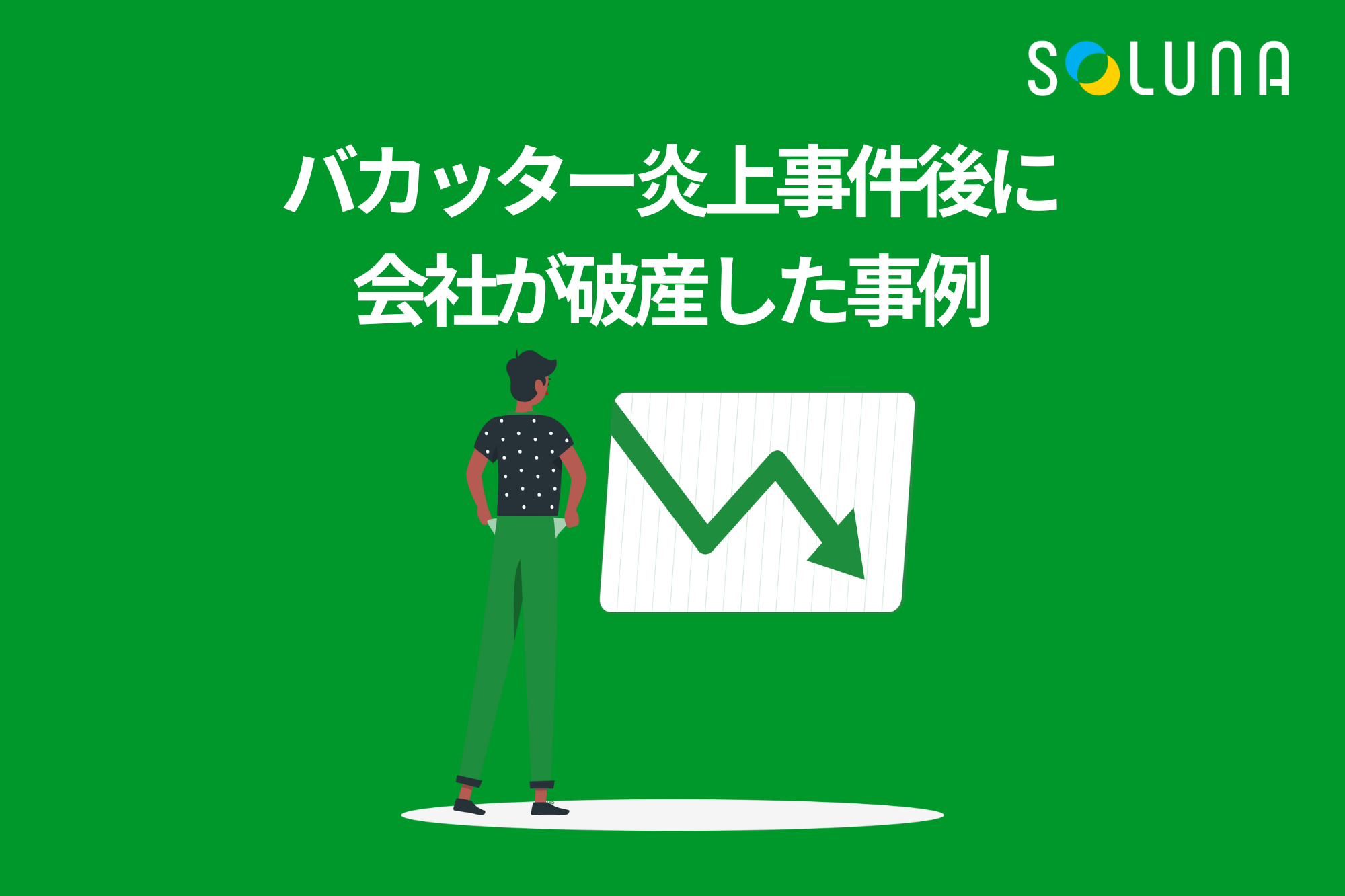【事例あり】サジェスト汚染の3つの原因!4つの対処法と放置するリスクを解説
- 対策方法
- 検索エンジン
サジェスト汚染が発生すると、売上減少や人材確保の難化など、企業に対してさまざまな悪影響を及ぼします。その一方で「サジェスト汚染はなぜ起こるのか分からない」という方も多いのではないでしょうか。
そこで今回の記事では、サジェスト汚染の3つの原因と4つの対処法について詳しく解説します。放置するリスクやサジェスト汚染の事例も紹介するので、広報担当の方はぜひ参考にしてみてください。
サジェスト汚染とは?概要を解説
サジェスト汚染とは、検索エンジンのサジェストにネガティブな印象を与えるキーワードが表示されることです。例えば特定の企業名を検索した際に「ブラック」「不正」「倒産」などがサジェストに表示されるケースが挙げられます。ネガティブなキーワードはユーザーの興味をひきやすく、優先的にクリックされやすい傾向があります。
サジェスト機能はユーザーが素早く検索できる一方で、表示されるキーワードによっては風評被害につながるリスクがある点に注意が必要です。また検索エンジンでは、ユーザーにクリックされるほど上位表示されやすくなるため、企業はサジェスト汚染が発生する前に予防策を講じることが求められます。それでも実際にサジェスト汚染が発生してしまったときには、迅速な対応が不可欠です。
サジェスト汚染が発生する3つの原因
サジェスト汚染を解消するためには、発生した原因をつきとめることが大切です。ここでは、サジェスト汚染が発生する3つの原因を見ていきましょう。
- 第三者が故意に引き起こしている
- 類似する検索キーワードがある
- ネガティブなキーワードが多く検索されている
サジェスト汚染が発生した際は、原因に応じて適切な方法で対処する必要があります。あらかじめ主な原因を把握しておくことで、スムーズな解決が可能となります。
第三者が故意に引き起こしている
サジェストキーワードは、ユーザーの検索履歴や検索傾向などの要素をもとに決まります。この仕組みを悪用すると、意図的にサジェスト汚染を引き起こすことができます。サジェスト汚染を故意に引き起こす理由は、企業に対する恨みや競合他社による妨害のほか、単なる好奇心などさまざまです。
具体的には「〇〇社 ブラック」「〇〇社 倒産」などのキーワードで大量に検索したり、特定のWebサイトやSNSアカウントで同じ内容を何度も投稿したりします。その結果、検索エンジンにネガティブなキーワードはユーザーのニーズが高いと認識され、サジェストに表示されるようになります。
類似する検索キーワードがある
企業名や自社のサービス・商品名に類似したキーワードが存在する場合、意図せずサジェスト汚染が発生することもあります。例えば名前の似た企業が不祥事を起こした際に、ユーザーが誤認して「自社名+ネガティブなキーワード」で検索するケースです。
サジェストキーワードは検索ボリュームによって変わるので、勘違いするユーザーが多ければ多いほど上位表示されてしまいます。またユーザーが検索していない場合でも、検索エンジンが類似キーワードと混同してしまい、サジェストに表示されることもあります。
ネガティブなキーワードが多く検索されている
サジェストキーワードは、ユーザーの検索ボリュームによって決まる仕組みです。そのため企業で何らかの問題が起こった際に、ネガティブなキーワードとともに頻繁に検索されると、サジェストに反映されてしまいます。
特に、SNSやニュースサイトで取り上げられた情報が、サジェストキーワードに大きな影響を与えます。仮に事実とは異なる場合でも、ユーザーが正しい情報として受け取ってしまうケースは少なくありません。その結果、企業イメージが低下して風評被害につながる可能性が高まります。
サジェスト汚染が発生したときの4つの対処法
サジェスト汚染は、どの企業にも起こりうるトラブルです。ここでは、具体的な対処法を4つ見ていきましょう。
- Googleにサジェストの削除申請をする
- ネガティブな情報の発信元に削除を依頼する
- 弁護士に依頼する
- サジェスト汚染の対策業者に依頼する
サジェストにネガティブなキーワードが含まれると、企業イメージの低下につながります。そのためサジェスト汚染が発生した際は、迅速かつ適切な方法で対処することが大切です。
Googleにサジェストの削除申請をする
Googleでは、不適切なサジェストキーワードに関してユーザーからの削除申請を受け付けています。以下の項目に該当するキーワードは、特に削除してもらえる可能性が高いです。
- 危険なコンテンツ
- ハラスメント コンテンツ
- ヘイト コンテンツ
- 露骨な性表現を含むコンテンツ
- テロに関するコンテンツ
- 暴力や流血
- 下品な言葉や冒涜的表現
上記に加えて、中傷的な言葉も削除の対象となる場合があります。ただし申請すれば、必ず不適切なサジェストキーワードが削除されるとは限りません。単なるネガティブな表現や批判的な言葉だけでは、審査に通りづらいのが現状です。
ネガティブな情報の発信元に削除を依頼する
サジェスト汚染の原因がWebサイトやSNSの投稿だった場合は、ネガティブな情報の発信元に削除依頼するのも有効な手段です。サジェストはインターネット上の情報とも関連があるので、不適切な投稿がなくなれば、表示されなくなる可能性があります。
Webサイトには一般的に「お問い合わせフォーム」が用意されているので、そこからサジェスト汚染の原因となったコンテンツの削除を求めましょう。ただし発信元が匿名だった場合、削除依頼に応じてもらえない可能性も考えられます。SNSの場合は、違反報告を行うことで削除されるケースがあります。
情報の発信者が削除してくれないときは、法的手段を検討しなければなりません。別の手段でも対処できるように、弁護士の選定や証拠集めなど、準備しておくことが大切です。
弁護士に依頼する
Googleや情報の発信元に対応してもらえないときは、弁護士に相談するのがおすすめです。弁護士は法的根拠を持って依頼できるため、削除に応じてもらいやすくなります。またインターネットのトラブルに特化している弁護士は、開示請求や損害賠償請求など、裁判もサポートしてくれる点が魅力です。
弁護士費用はかかりますが、サジェスト汚染を確実に解決する有効な手段となります。ただし再発防止の対策までは行えないため、予防したい場合はサジェスト汚染の専門業者に依頼する必要があります。
サジェスト汚染の対策業者に依頼する
サジェスト汚染を解決するだけでなく、再発防止にも努めたい場合は、専門の対策業者に依頼しましょう。弁護士に依頼して不適切なサジェストキーワードを削除することも重要ですが、再発リスクはなくならないため、根本的な解決までには至りません。
一方でサジェスト汚染に特化した業者に依頼すれば、インターネットの誹謗中傷や風評被害も含めた対策が可能となります。予防策を一任できるため、企業に悪影響を及ぼすインターネットトラブルの発生リスクを最小限に抑えられます。
ソルナ株式会社の「カイシャの病院」では、効果的な風評被害対策を行っています。お客様の状況に合わせて最適な対策を実施することで、迅速な問題解決が可能です。
サジェスト汚染を放置する3つのリスク
サジェスト汚染は、企業に悪影響を及ぼします。ここでは、サジェスト汚染を放置する3つのリスクを見ていきましょう。
- 売上が減少する
- 企業の信頼が低下する
- 人材確保が難しくなる
サジェスト汚染を放置すると、さまざまなトラブルに発展しやすくなります。いずれの問題もすぐに解決できないため、サジェスト汚染は早い段階で対処することが大切です。
売上が減少する
サジェスト汚染を放置すると顧客の購買意欲が低下し、売上の減少につながる可能性が高まります。ユーザーが企業名やサービス・商品名を検索した際に、ネガティブな言葉がサジェストに表示されると企業への不信感が生じ、購入を避けるためです。
特にBtoCビジネスの場合、顧客は購入を決める際にインターネットの口コミを重視する傾向が強いので、サジェスト汚染の影響を大きく受けます。サービスや商品の質に満足している既存顧客であっても、ネガティブなキーワードを目にすると不安が募り、競合他社を選択するケースが考えられます。
企業の信頼が低下する
サジェスト汚染によって企業の信頼が低下すると、回復するためには多大なコストと時間がかかります。消費者や取引先からの信頼を失うと売上減少につながりますが、ステークホルダーの場合は資金調達に悪影響を与えかねません。
検索エンジンの情報は一つの判断材料となるため、ネガティブな言葉がサジェストに表示されると、融資の審査に落ちたり、投資してもらえなくなったりするケースがあります。資金繰りが苦しくなると資金不足や経営悪化につながり、最終的には倒産を招く可能性も考えられます。
人材確保が難しくなる
サジェスト汚染によって企業のイメージが低下すると、新たな人材を採用するのが難しくなります。求職者が企業のネガティブな情報を見ることで、応募を避ける可能性があるためです。特に若年層の求職者はインターネットの情報を重視する傾向があり、転職市場ではさまざまな口コミサイトが利用されています。
優秀な人材は他社へ流れてしまうため、結果的に企業の競争力が失われてしまう可能性も高いです。また、自社の評判が悪くなることで従業員のモチベーションが低下し、離職率が上昇するリスクも考えられます。
サジェスト汚染の企業事例
サジェスト汚染はどの企業でも発生する可能性があり、放置すると大きな問題に発展しやすいトラブルです。実際にサジェスト汚染が発生し、企業のイメージが低下したケースは数多くあります。ここでは、サジェスト汚染の2つの企業事例を見ていきましょう。サジェスト汚染が発生した経緯は、自社で予防策を講じる際の参考になります。
某アイスチェーン店
某アイスチェーン店は、人気ゲームアプリとのコラボレーションを実施しました。その結果、検索エンジンのサジェスト機能に「まずい」や「毒」などのネガティブなキーワードが表示されるようになった事例です。
コラボしたゲームでは、ポイントを取りづらい場所を「まずい」と表現します。「毒」は相手を倒すためのスキルに関連する言葉です。しかし実際にプレイしたことがないユーザーには誤解を招く表現となりました。このように異なる意味での検索が、サジェスト汚染につながってしまうケースもあります。
某食品製造メーカー
某食品製造メーカーは、消費者が購入した商品に虫の死骸が入っていたとSNSに投稿したことがきっかけで、インターネット上で炎上しました。そのため某食品製造メーカーは自主回収に加えて一時的に商品の販売を中止し、製造ラインの見直しや衛生管理の強化などの対策を講じました。
しかし多くのユーザーに拡散された結果、検索エンジンのサジェストには「ゴキブリ」「異物」といったネガティブなキーワードが表示されてしまった事例です。現在は新商品の開発や積極的なマーケティング活動により、ネガティブなサジェストキーワードは上位から排除されています。
サジェスト汚染が発生したら迅速な対応が不可欠
サジェストは検索候補が表示されるため、ユーザーの利便性が向上する機能です。その一方でサジェスト汚染が発生し、企業に悪影響を及ぼすリスクがあります。サジェスト汚染は企業に原因があるケースが多いものの、第三者が故意的に引き起こしている場合もあるのが現状です。
サジェスト汚染は放置すると、売上や企業の信頼性の低下、人材確保の難化につながります。どの企業にも起こりうるトラブルなので、企業はスムーズに対処できるようにしておきましょう。
またサジェスト汚染を根本的に解決するためには、専門業者に依頼して再発防止の予防策を講じる必要があります。ソルナ株式会社の「カイシャの病院」では、状況に応じて効果的な風評被害対策を行うことが可能です。サジェスト汚染の対処だけでなく、しっかり予防もしたいという方は、ぜひ一度お気軽にお問い合わせください。