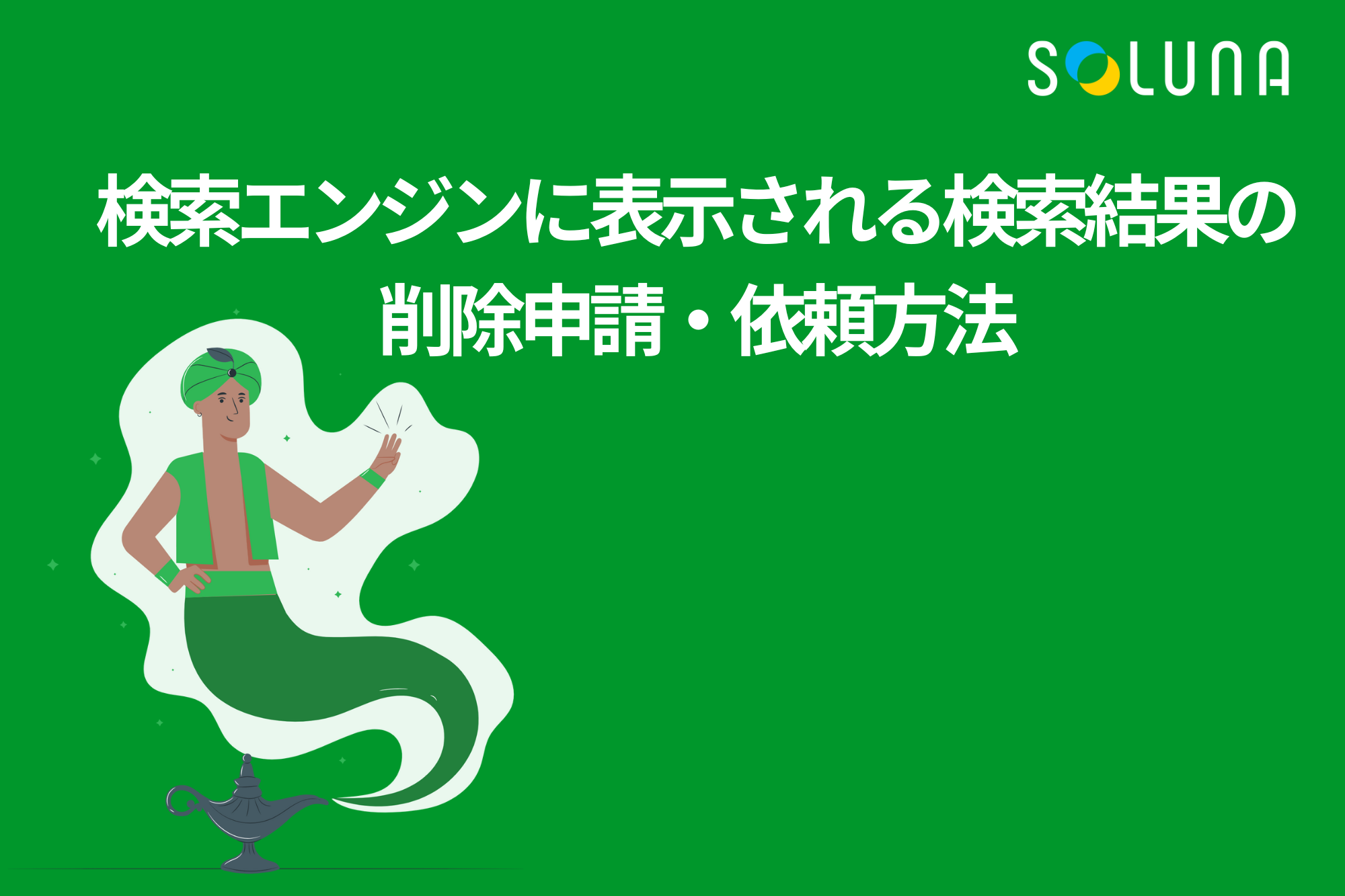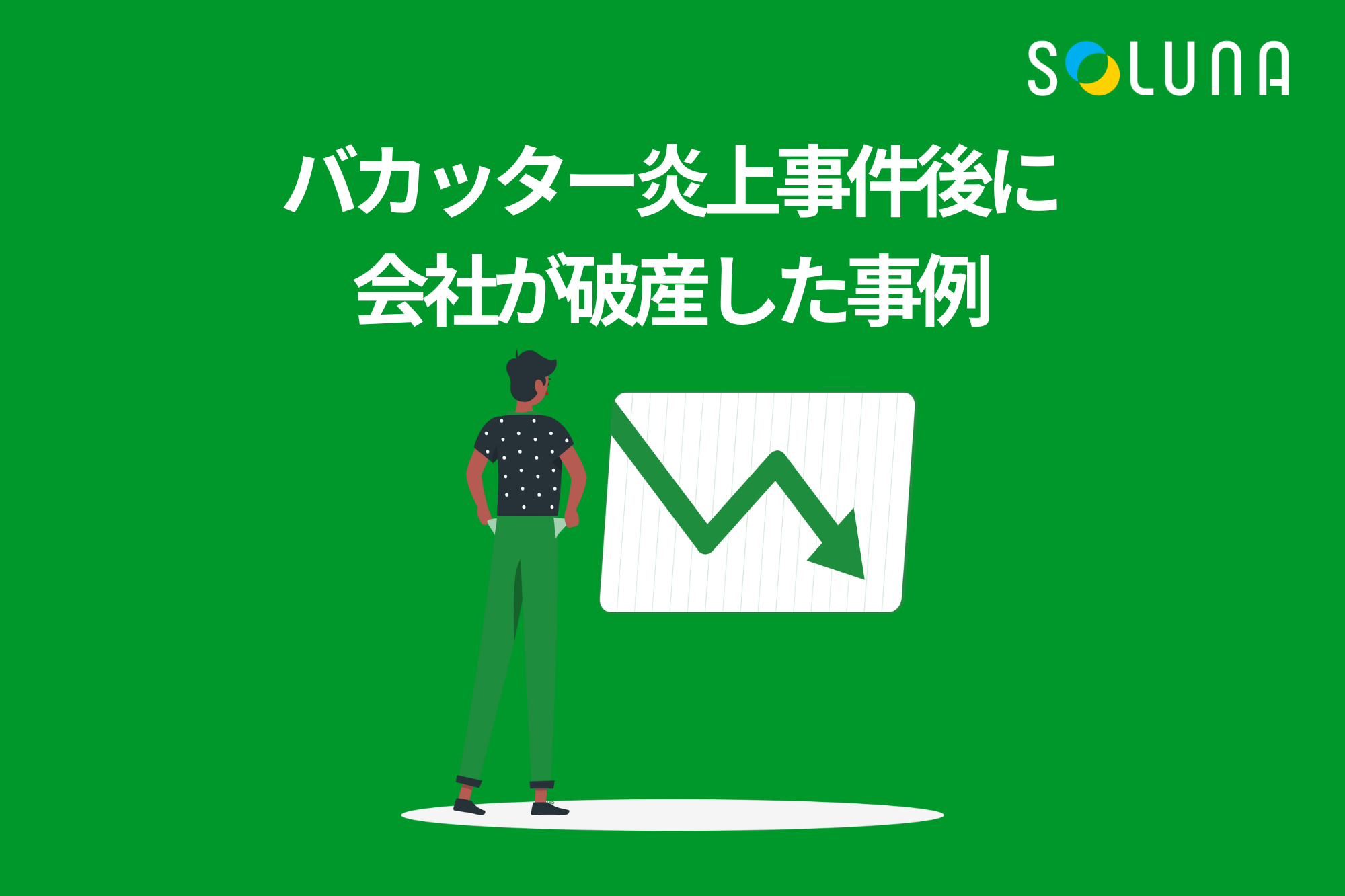風評被害につながる投稿を削除する3つの方法!依頼を行う手順も解説
- 対策方法
- 風評被害
インターネット上で広がる風評被害は、内容によっては個人や企業にとって致命的な影響を及ぼします。誤った情報や悪意のある投稿の拡散により、信頼や評判が一瞬で崩れてしまうこともあるでしょう。そのような状況で被害を最小限に抑える方法の1つに、投稿の削除依頼があります。
そこで本記事では、風評被害につながる投稿を削除する方法を解説します。インターネット上で不正確な情報や悪質な投稿に悩まされている方は、ぜひ参考にしてみてください。
風評被害につながるとして削除依頼できる3つの投稿内容
風評被害を防ぐためには、インターネット上に拡散された不正確な情報や誤解を招く投稿に対する迅速な対応が必要です。特に企業や個人の評判に深刻な影響を及ぼす可能性のある投稿に対しては、迅速に削除依頼を行いましょう。この章では削除依頼ができる3つの投稿内容を紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。
事実に基づかない虚偽の情報
誤った情報や噂は意図的に作り上げられる場合もあれば、単なる誤解や勘違いから発生することもあります。特にインターネット上は匿名で気軽に発信できるため、責任を持たないまま誹謗中傷や虚偽の情報を流される場合が多いです。根拠がない情報を広める投稿は法的に問題を引き起こす可能性があるため、投稿者にも責任を問える場合があります。正確で信頼できる情報を守るためにも、事実に基づかない内容は削除対象となる可能性が高いです。
個人や企業の名誉を傷つける内容
個人や企業の名誉を傷つける内容は、名誉毀損や誹謗中傷に該当する場合があります。対象となる人や企業の社会的評価を著しく低下させることがあり、削除や法的手続きを求める根拠として扱われることが多いです。
たとえ事実であっても、個人のプライバシーを侵害する内容を投稿してはなりません。公開された情報が個人の社会的評価を低下させるようなものであった場合、名誉毀損の対象となる可能性が高いです。
商標権や著作権を侵害する投稿
商標権や著作権侵害となる投稿は知的財産権を侵す内容であり、法的に問題となる場合があります。商標や著作物を無断で使用することは、権利者に損害を与える可能性が高いです。特に、商業目的で使用している場合は違法性を主張できます。
他社のロゴやブランド名を利用する場合は事前に使用許可を得る、もしくは適切なライセンス契約を結ばなければなりません。各プラットフォームでは著作権や商標権侵害に関するポリシーを設けており、削除依頼の対象として扱われる場合が多いです。
風評被害につながる投稿を削除する3つの方法
風評被害につながる投稿の拡散は、企業や個人にとって大きなリスクとなります。そのため早急に対応し、適切な方法で削除することが重要です。投稿を削除する方法は、以下の3つがあります。
- サイト管理者に対する削除依頼
- 送信防止措置依頼
- 検索エンジンに対する削除依頼
この章では風評被害を防ぐために有効な投稿削除の方法を紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。
サイト管理者に対する削除依頼
サイトの管理者に対して、問題のある投稿を削除してもらうよう依頼する方法です。削除依頼を出す前に、まずは問題の投稿内容が本当に風評被害に該当するかを確認しましょう。具体的には、以下の項目に該当しているかをチェックします。
- 虚偽の情報
- 名誉毀損
- 誹謗中傷
上記のような法的に問題がある投稿内容であった場合、まず証拠として保存しておきましょう。スクリーンショット撮影やURLの保存などにより、投稿者の名前や日時を記録しておくことが重要です。サイトの利用規約を確認し、違反していることを明確にしましょう。
多くのサイトでは、削除依頼を受け付ける専用のフォームや連絡先を設けています。専用のフォームがない場合は、サイトのサポート窓口や問い合わせ先に削除依頼を行います。削除依頼を行う際は、以下のように内容を具体的かつ明確に伝えることが大切です。
- 投稿の詳細(URL、投稿者名、投稿日時など)
- 削除を求める理由(名誉毀損や虚偽の内容であること、利用規約違反など)
- 証拠の提供(スクリーンショットや証明資料など)
- 削除を求める期限
サイト管理者に対して明確かつ詳細な内容を伝えることで、問題の投稿の迅速な確認とスムーズな削除対応が期待できます。ただし、必ずしも削除してもらえるとは限らない点に注意しましょう。
送信防止措置依頼
送信防止措置とは特定のコンテンツが引き続き公開されることを防ぐために、問題のある投稿の削除やアクセス制限を求める手続きです。誹謗中傷や虚偽の情報が広がっている場合、迅速に対応するためには送信防止措置依頼が効果的です。ただし、事前に問題の投稿が風評被害につながっていることを確認する必要があります。具体的には、以下の点を確認しましょう。
- 投稿内容
- 投稿者の情報
- 拡散状況
証拠を収集することで、送信防止措置を依頼する際に必要な根拠を明確にできます。送信防止措置依頼受付専用の窓口やフォームを利用し、サイト管理者への削除依頼の場合と同様の内容を記載します。しかし「情報が事実に基づいている」「公正な意見や評価である」とみなされた場合は、送信防止措置を拒否される可能性があることを理解しておきましょう。
検索エンジンに対する削除請求
風評被害が広がる原因の1つとして、検索エンジンによる表示があります。問題のある投稿や誹謗中傷が検索結果に表示され続けると、企業や個人に深刻な影響を与える可能性が高いです。削除請求を行う前に、検索エンジンがどのような基準で情報を表示しているかを理解しておきましょう。
検索エンジンへの削除請求は、各検索エンジンのサポートページやヘルプセンターを通じて行います。削除請求の際には、以下の情報を提供して判断してもらいます。
- 削除を求めるURL
- 削除理由
- 関連する証拠
削除請求を行う際は証拠を整え、理由を明確にして正当な手続きに則って依頼を行うことが大切です。名誉毀損や誹謗中傷など具体的な理由を示し、情報を削除すべき理由が正当であることを主張する必要があります。削除依頼を拒否された場合は理由を確認し「再度申し立てを行う」もしくは「法的手段の検討」を行いましょう。
風評被害につながる投稿の削除依頼を行う手順
風評被害が発生した場合やネガティブな投稿を発見した際は、早急な対応が必要です。しかし依頼が必ずしも受け入れられるとは限りません。ここでは、スムーズに削除してもらうために必要な準備を理解しておきましょう。
事実確認
削除を依頼する前に、投稿内容の事実確認を行いましょう。投稿されている情報が「事実に基づいているか」「単なる噂や誤情報であるか」を慎重に調べておくことが重要です。事実確認を行わずに削除依頼を出してしまうと、投稿者やプラットフォーム側から「言論の自由を侵害する」と反論される可能性もあるため注意が必要です。
被害の客観的な証明
事実確認ができたら、該当の投稿がどれほどの影響を及ぼしているかを評価します。風評被害の影響が単なる印象や感情の問題ではなく、実際に企業や個人に経済的・社会的なダメージを与えていることを示すことが重要です。被害の内容を適切に証明することができなければ、投稿の削除を求めても受け入れられない場合があります。
風評被害が実際に発生したことを示す証拠を集め、プラットフォーム側や法的機関に対して強い根拠を持って対応しましょう。証拠として利用できるのは、以下のようなものがあります。
- 売上や業績の低下を示すデータ
- 取引先や顧客からの反応
- 第三者の証言や報告書
客観的な証明を行うことで、削除依頼のスムーズな進行につながります。
削除の正当性を検証
風評被害の投稿に対して削除依頼を行う際、正当性を十分に検証する必要があります。削除依頼の正当性を慎重に確認せずに削除依頼を行うと、要望が受け入れられないだけでなく、トラブルを招くことにもなりかねません。各プラットフォームに設けられている利用規約やポリシーを確認し、投稿内容が違反していることを明確にしましょう。
該当の投稿が「どのように事実を歪曲しているか」「どの点が問題であるか」を具体的に説明し、プラットフォーム側に削除依頼する正当な根拠を示すことが大切です。削除依頼の正当性を検証することで投稿が不当であることの証明になり、後々のトラブルを避けられます。
削除依頼以外の風評被害を解決する方法
削除依頼は必ずしも受け入れられるとは限らないため、ほかの手段を使って風評被害対策を講じる必要があります。この章では、3つの対策を紹介するので参考にしてみてください。
評判改善
評判改善とは企業や個人の信頼性を回復し、ポジティブなイメージを築くための長期的な戦略です。風評被害につながる投稿の削除依頼を行って情報を取り除くだけでは、完全に問題が解決するわけではありません。
悪影響を最小限に抑えるためには、誤解を解消してポジティブな情報を発信し続けることが大切です。評判改善の具体的な方法には、企業の透明性を高める取り組みや顧客からの信頼を回復するためのコミュニケーション戦略などがあります。
例えばSNSやブログを活用して誠実かつ積極的に情報発信を行うことで、風評被害に対する反論や説明を効果的に行えます。顧客の声やレビューを大切にし、問題解決に向けた姿勢を見せることも信頼回復につながるでしょう。評判改善は風評被害が発生する前から日々行っておくべき継続的な活動であり、企業のブランド価値やイメージの向上を目指す取り組みです。
逆SEO
逆SEOとは、検索エンジン結果ページに表示されているネガティブなコンテンツの順位を下位に押し下げる手法です。削除対応や送信防止措置が難しい場合や、依頼を拒否されたときの代替手段となり得ます。
逆SEOの目的は、風評被害を引き起こしているページや情報が検索結果で上位に表示されるのを防ぎ、良い評価やポジティブなコンテンツを上位にランクインさせることです。否定的な情報が目に触れにくくなり、企業や個人の評判を守れます。逆SEOの主な手法は、以下のとおりです。
- 良質なコンテンツの作成と発信
- SEO最適化
- 信頼性のあるウェブサイトでのコンテンツ公開
- 悪質なリンクの削除
逆SEOは良質なコンテンツの発信を続けることで、長期的に安定した結果が期待できるメリットがあります。投稿が削除されない場合でも、逆SEOを活用することで風評被害対策の効果を高められるでしょう。
しかし逆SEOは、良質なコンテンツを積み重ねる手法であるため、成果が出るまでに時間がかかります。完全にネガティブな情報を消すわけではないため、根本的な解決にならない場合があることを理解しておく必要があります。
法的措置
削除依頼や逆SEOなどで風評被害を解決できない場合は、法的措置による風評被害の拡大防止を検討しましょう。法的措置であれば、問題となるコンテンツに対して強制力を持った対処が可能です。風評被害に対して取るべき法的措置の種類は、以下のとおりです。
- 名誉毀損による損害賠償請求
- 削除請求訴訟
- 仮処分命令
- 刑事告訴
仮処分や削除請求訴訟は強制力があるため、問題のある投稿を法的に排除できます。法的措置は、迅速な対応と被害拡大防止の効果が期待できる点がメリットです。ただし、裁判を起こすには法的手続きが必要となるため、時間と費用がかかる場合があります。
また、訴訟や告訴が成立しないこともあるため、100%の成功を保証するものではありません。裁判相手に反論の機会を与えることになるため、さらなる対立を引き起こす可能性があることを理解しておく必要があります。法的措置をとる場合は、適切な証拠の収集と専門家の支援が必要です。
風評被害につながる投稿の削除依頼は専門業者へ相談しよう
インターネットが普及する現代では、さまざまな情報が瞬時に拡散されるため風評被害が拡大しやすい状況です。そのため、ネガティブな投稿へは迅速かつ適切な対応が求められます。まず風評被害が発生した際は問題の投稿の「事実確認」を行い、情報が虚偽であることを明確にしてからサイト管理者への削除請求や送信防止措置を依頼しましょう。
しかし、削除依頼だけでは根本的な解決は難しいため、風評被害対策の専門業者への依頼をおすすめします。ソルナ株式会社の「カイシャの病院」は、悪質な風評被害による問題を解決する専門機関です。ブランドドクター1級を有する資格者が、さまざまな専門性を持つパートナーと共に最善策を提案いたします。風評被害対策や再発防止をしたい企業さまは、ぜひ下記のお問い合わせフォームよりご相談ください。